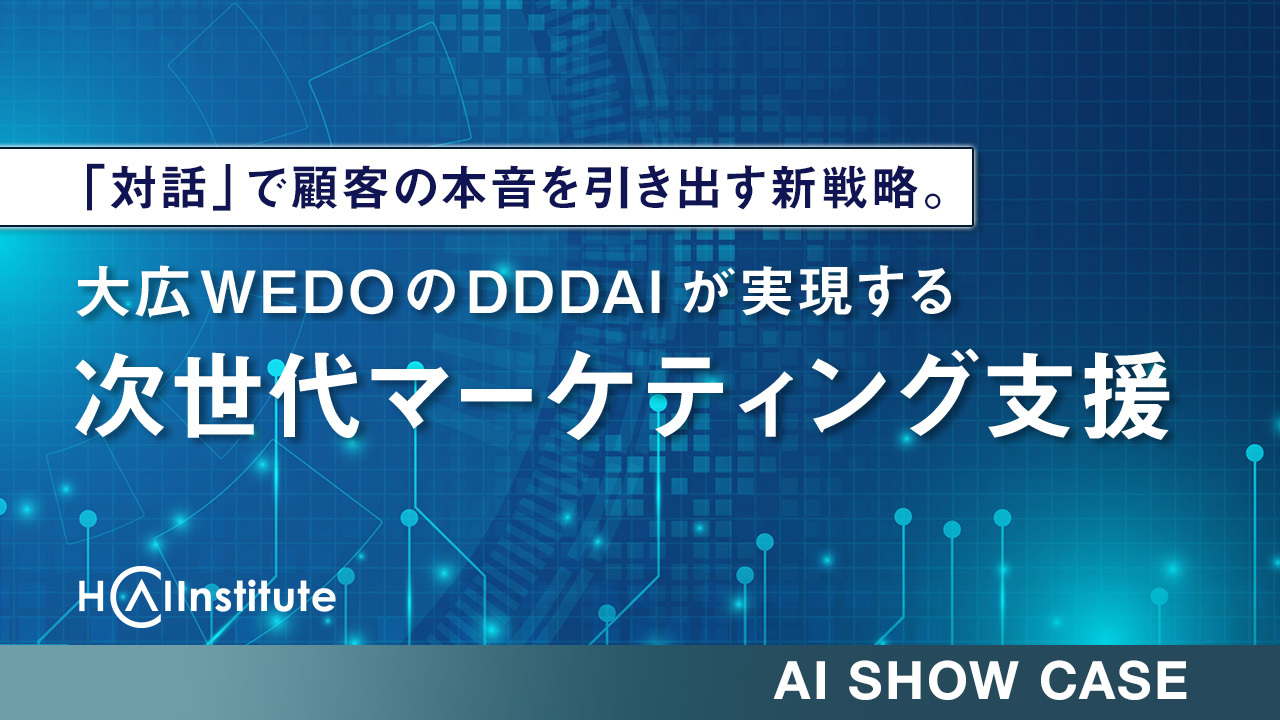
「対話」で顧客の本音を引き出す新戦略。大広WEDOのDDDA
「生成AIを活用したいが、顧客の本音をどう引き出せばよいかわからない」「従来の調査では見えない潜在ニーズを探りたい」――こうした声は、今やマーケティングの現場で頻繁に聞かれるようになった。
そうした中、株式会社大広WEDOが2024年9月にローンチした「DDDAI(Deep Dialogue デザイン-AI)」は、顧客とAIとの対話を通じて企業のマーケティング支援を行う革新的なプラットフォームとして注目されている。
従来のデータ分析だけでは捉えきれない顧客の本音や潜在的なニーズを、AIとの対話を通じて引き出すという新しいアプローチから、企業のAI活用における新たな可能性を探る。
AIが引き出す顧客の本音
DDDAIの開発において最も重要な着想は、「AIの方が自然に自己防衛の壁を取っ払って話しやすい」という観点だった。
例えば、ハラスメントの相談窓口をAIにしてほしいという意見。ホテルでのシーツ交換を電話ではなくチャットで気軽にリクエストできるという経験。こうした事例から、AIを介することで人間が本音を話しやすくなる場面が確実に存在する、という考えがプロダクトの原点にある。
人間同士の対話では、立場や関係性によって本音が引き出しにくい場面がある。しかし、AIとの対話であれば、より率直な意見や感情を表現しやすくなる。「間違っている」と言われても恥ずかしくないからだ。
さらに、データだけを見て推測することの限界もある。購買履歴などのデータから顧客の嗜好を推測しても、実際の本音は全く異なる場合がある。企業にはコールセンターなど直接の接点があるのだから、何かあれば聞けばよいだろう。ただし、1対1のライトな対話を人的に行うことは現在のコールセンターでは実質不可能である。
そこで生まれたのが、AIで対話を行い、履歴を蓄積して展開していくというアプローチだった。
ベクトル検索で膨大な声から本質を抽出
従来、コールセンターには膨大なインプットがある。しかし、その中からロジカルに有効な声を抽出することは極めて困難だった。
クレームなど大きな声だけに注力してしまう。感覚的に本質的ではない部分を参考にしてしまう。こうした人的なエラーが起きがちだった。
この課題に対して、DDDAIではOpenAIのベクトル検索の仕組みを活用している。ベクトル検索であれば、文脈や方向性を抽出できるため、効果的な分析が可能になる。
ただし、日本語特有の課題もある。前置きが長い。修飾語が多い。こうした特徴が精度を下げる要因になることもある。
そこで重要になるのが、分析にあたって「雑味」を消すことだ。GPTに読み込ませ、テキストを加工して濃度の高いものでベクトル検索をかけると、効果的な結果が得られる。興味深いことに、コールセンターの対話データは比較的ベクトル検索に適している。余分な言葉が少なく、本質的な部分に集中しているからだ。
3つのAIツールが連携する統合プラットフォーム
DDDAIは、対話をテーマに設計された3つのAIツール群で構成されている。「TribeAI」「BrandDialogueAI」「 DDDAI トイノワ が、それぞれ単独で活用できるとともに、連携することで価値を最大化する仕組みとなっている。
TribeAIは、SNSなどの顧客同士の対話をAIが分析し、ブランド・商品にまつわる価値観の塊(トライブ)に分類して顧客の姿を明らかにする機能である。新商品発売後の反応分析などを素早く行え、PDCAサイクルを回しやすくなる。
つぎにBrandDialogueAIは、システムの心臓部とも言える機能。ChatGPTにブランド人格を付与し、各企業が保有する顧客データや商品データを基にしたダイナミックプロンプト技術を通じて、各顧客とOne to Oneの対話を実施するAIチャットボットである。
仕組みはまず、ブランドとして必要な外部知識をRAGデータとして保持する。ブランドとして必須の内容を固定プロンプトで記述してブランド人格を設定する。そのうえで、対話する顧客の情報や対話内容に関する情報をRAGデータから抽出して動的プロンプトを生成し、対話を行う。
最後に DDDAI トイノワは、AI同士のワークショップにより新たな価値創出を支援する技術である。単独でも活用できるほか、他のツールと連携したソリューションの提案も可能となっている。
FABRIC TOKYOで実証。F2転換率10pt以上向上
DDDAIの効果は、FABRIC TOKYOとの実証実験において確認することができた。
同社のブランド人格に優秀な販売スタッフの知識ベースを組み合わせ、「コーダイ by FABRIC TOKYO」というコーディネーターAIとして実装。LINE公式アカウントのトークルーム上で顧客と対話を行った。
その結果、初回購入客(F1)から2回目以降の購入客(F2)への転換率が10pt以上上昇したのである。さらに、FABRIC TOKYOでは購入データとアンケートによる嗜好性データを基に個別の提案を行う仕組みが構築できた。
重要なのは、購入した商品や好み以外のユーザー情報も把握できることだった。勤めている企業が毎日スーツを着なければいけないのか。カジュアルでもよいのか。普段どういう服で日常を過ごしているのか。こうした情報に基づいて適切な答えを返すため、同じ天気、同じ場所に行く場合でも、その人のライフスタイルに合わせて全く異なる提案を行える。
F2転換率向上の背景要因
FABRIC TOKYOでの効果的な結果を生み出した要因をさらに紐解くと、複数の要素が組み合わさっていることがわかる。
まず注目すべきは、購入後の対話のしやすさだ。AIには不満や感想を言いやすいので、「どうでしたか」「不満はありましたか」といった対話がしやすい。対話のしやすさは、対話量の増加に直結し、結果としてエンゲージメントが高まった。
また、AIの適切な対応も必要だ。顧客の声に対して、「申し訳ございません。次回はこのようなおすすめをさせていただきます」といった適切かつスピーディーな提案ができた。これがF1からF2への転換のきっかけになっている。
さらに、戦略的な対話設計も効果的だった。FABRIC TOKYOはカスタムオーダーのビジネスウェアブランドだが、スーツは頻繁に購入されるものではない。そこで、シャツやポロシャツ、付属品など、比較的購入頻度の高い商品に焦点を当てた対話を最初から組み立てていた。
効果的な対話を実現する設計
さらに、より高い効果を実現するために、DDDAIではユーザーの話を引き出すためのいくつかの工夫が施されている。
まず、AI側の発話量を減らすことを意識している。理想は全体の50%以下に抑えることだ。ユーザーにより多く話してもらうことが目的である。
質問の仕方も気にするべき要素だ。「どう思われますか?」というように、ある程度自由度を持たせつつ意見を聞くようにしている。ただし、自由度が高すぎると逆に答えにくくなることもある。そこで、最初はYes/No形式の質問から始めて、そこから話題を広げていくテクニックを使っている。
コーディネーターなどの専門家のノウハウも活用している。彼らの知識をトークスクリプトに落とし込んで、ユーザーが自然に、たくさん話せるような流れを作る点も特徴的だ。
継続的な顧客関係構築へ
DDDAIの今後の展望として、顧客との対話を継続する機能の向上が重要な課題となっている。適切な頻度で心地よい対話を続けることが重要だが、距離感の調整が課題だ。
毎日5通も来ると、かえって関係性が悪くなる可能性がある。理想的なのは、顧客にとって心地よい関係性を保てるコミュニケーション量である。例えば週1、2回程度の頻度が適切とされている。
また、蓄積したデータをクリエイションやマーケティングに活用することも進められている。さらに、AIによるブランド自体の変化の可能性も考えられる。顧客の声をリアルタイムで反映し、ブランドを進化させていく取り組みである。
今後の社会では、さらにダイバーシティが進む。多様な人の価値観を統合してブランディングを考えることが必要になる。人間はせいぜい2次元か3次元程度での判断しかできない。多次元の価値観をロジカルに分析して方向性を出すには、AIの力が不可欠なのである。
DDDAIが示すのは、AIを単なる自動化ツールとして捉えるのではなく、顧客の本音を引き出し、ブランドと顧客の関係性を豊かにする存在として活用する新たな可能性だ。従来のマーケティングでは困難だった深い顧客理解と効果的な施策立案の実現により、企業のマーケティング活動に革新をもたらすことが期待される。

