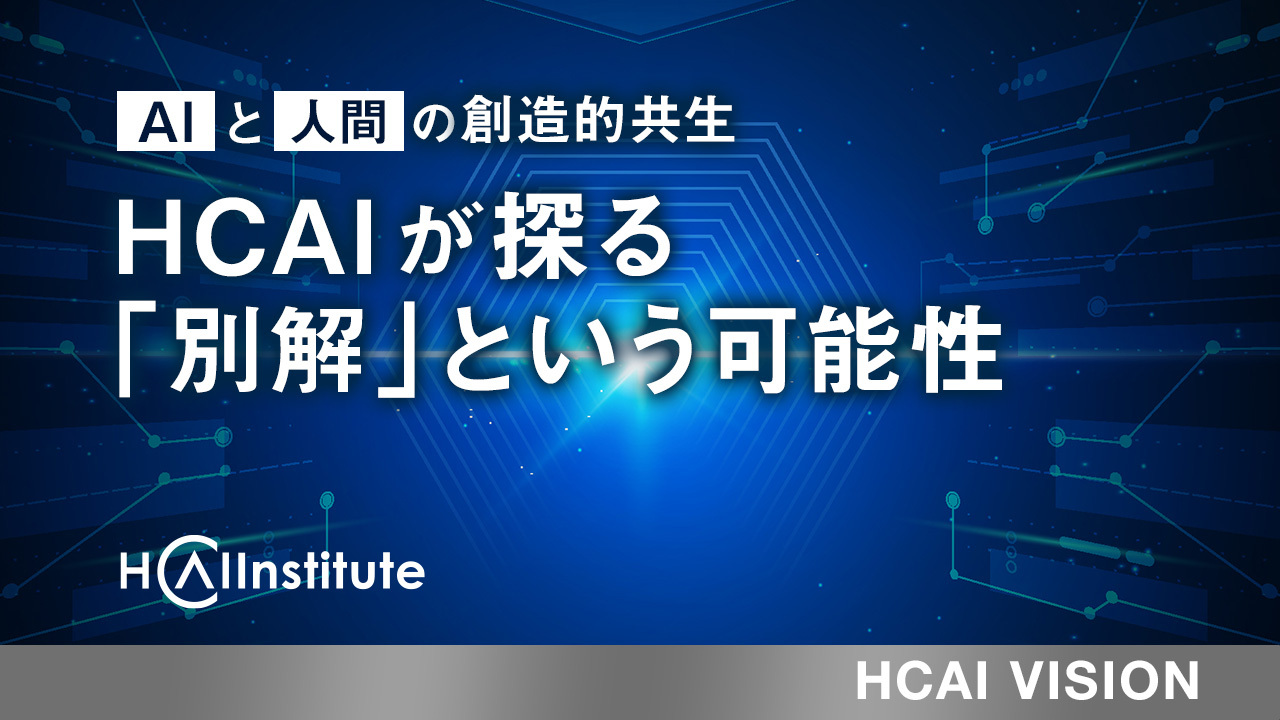
AIと人間の創造的共生。
生成AIが社会に浸透し始める中、その活用方法については様々な議論が行われている。効率化やコスト削減といった従来の視点を超えて、人間とAIの新たな関係性を模索する試みが世界各地で始まっている。
そんな中、博報堂DYホールディングスが2024年4月に設立した「Human-Centered AI Institute(以下、HCAI)」は、「人間中心のAI」を掲げ、技術と人間性が共鳴する社会の在り方を探っている。本稿では、HCAIにおける取り組みをもとに、同研究所が重視する「別解」という視点、人間の創造性との関係、さらにはAIと人間の調和的共生の可能性について考察する。
「人間中心のAI」が意味するもの
HCAIでは、「人間中心のAI」という概念のもと、人間とAIの新たな関係性を模索している。この考え方は、AIを作業の補助役として捉えるのではなく、新しい発想を引き出す存在と捉え、そこから生まれるコラボレーションや共創の可能性に注目している。従来の枠組みでは難しかった領域においても、AIとの協働によって新たな挑戦が可能になるとの期待がある。
一例として、人間に固有の「脆弱性」や「不安定さ」に、創造的プロセスとの関係を見出そうとする視点がある。
たとえば、「飽き」や「疲れ」といった状態は、集中力の喪失や一時的な作業中断を引き起こすが、そうした時間を挟むことで、思いもよらない視点や発想が生まれる場合がある。休息や気晴らしの後に、新たなアイデアや別の切り口が自然と浮かぶといった経験は、多くの場面で見られるものである。
このように、一見すると非効率に見える人間の状態や行動が、非線形な思考やクリエイティビティの起点になることもある。こうした不安定さこそが、論理や経験の積み重ねだけではたどり着けない新しい発想や視点を生み出すきっかけになる可能性があると考えられる。
誤差から生まれる創造的可能性──「別解」という視点
HCAIでは、AIに内在する不確実性や誤差に対し、それを単なる欠点として捉えるのではなく、思いがけない発想のきっかけとして前向きに捉える姿勢をとっている。
機械学習を基盤とする現代のAIは、確率統計処理に基づくため、一定のばらつきや誤差を含むことが構造上避けられない。この点に着目し、AIを「もう一つの可能性(別解)を提示する技術」として見直す取り組みを進めている。
たとえば、生成AIの「ハルシネーション」(AIが事実ではない情報を生成してしまう現象)も、一般的には問題視されがちだが、発想の幅を広げるきっかけとして活用できる場合がある。企画やアイデア出しの過程において、予想外の視点を提供する「壁打ち」の相手として、活用の余地があるとする見解である。
あわせて、HCAIでは「美意識」や「問いを立てる力」といった、人間固有の特性にも注目している。「AIは大量のデータを分析し、最大公約数的な結果を出すのは得意であるが、そこに美的判断や創造的意図が含まれるわけではない。そこに目的や意味を持たせたり、何を問いかけるかを考える力は人間に委ねられる。
クリエイティブなプロセスにおいて重要とされるのは、どのような問いを設定するかという点であり、答えそのもの以上に、問いの質が創造性を左右するという見方もある。AIの活用においても、正解を求めるだけではなく、新たな気づきや発見を導く問いをどのように立てるかが、協働の可能性を広げる鍵となる。
人間中心のAIと人間の「合気」から生まれる創造的調和
HCAIの森正弥が「人間中心のAI」を考えるうえで、もう一つ意識しているのが「合気(ハーモニー)」という視点である。
AIが人間に合わせてパーソナライズされるだけでなく、人間の側からも自身の考えや目的に応じてAIを柔軟に使いこなす。そうした双方向の関係が人とAIの自然な協働につながっている。
この「合気」という発想には、合気道における「気を合わせる」という感覚のように、人間らしい感性を、AIの研究や実装の中にも取り込んでいこうとする意識が含まれている。単に技術的な整合性を追うだけにとどまらず、より感性的・身体的な側面に配慮することが、今後の人間とAIの協働にとって重要な視点となりうる。
HCAIでは、AIと人間が一方的な主従関係ではなく、互いに呼吸を合わせ、調和する関係性が模索されている。それは、操作する側とされる側という一方向的な関係ではなく、感や対話から新しい価値を育てていくような関係である。
「クリエイティビティ・プラットフォーム」への移行とHCAIの中長期的展望
より中長期的な視点で見た時、HCAIは何を見据えるのか。
博報堂DYグループは2024年度からの中期経営計画において、「広告会社グループ」から「クリエイティビティ・プラットフォーム」への変革を宣言している。この戦略において、HCAIは中心的な立ち位置にいると言える。
博報堂DYグループは、これまでデータドリブンマーケティングに関する取り組みを積み重ねてきており、そこにAIを組み合わせる方向性についても一定の検討がなされてきた。2024年度からは『広告会社グループ』から『クリエイティビティ・プラットフォーム』への転換が掲げられているが、こうした展開は、これまでの流れの延長線上にある自然な方向性とも考えられる。
生成AIの普及に伴い、AIと人間の関係は今後さらに密接なものになると見られている。人間特有とされてきた創造的営みの領域においても、AIの関与が広がることが予想される。こうした変化の中で、HCAIではこれまでに得られた知見をもとに、AIの開発や活用が社会的に妥当なかたちで実装されていくよう後押ししていく。
技術の導入にあたっては、その適用が地域や文化の文脈においてどのようなかたちでなされるべきかという観点も含めて検討がなされている。特に、欧米におけるAI開発の潮流にそのまま倣うのではなく、日本の社会的・文化的背景を踏まえた独自の活用のあり方を模索する姿勢が必要であると考えられている。
人間中心のAIと人間の創造的共生がもたらす未来
HCAIが「人間中心のAI」という概念を通じて描く未来像は、AIと人間が対立するのではなく、互いの強みを活かしながら共に進化していく社会だ。
AIは人間の創造性を奪うものではなく、むしろそれを拡張し、これまでに実現が難しかったアイデアや協働の可能性を広げる存在として捉えることができる。人とAIが共にクリエイティブな力を発揮し合う関係性の中で、新たな表現や価値の創出につながる余地があると考えられている。
HCAIで実施した調査によれば、「AIによって世の中が変化する」と感じている生活者は6割を超えているという結果が得られている。こうした社会的な期待が高まる中において、変革が一方向的なものとならないよう、従来のAI原則やガバナンスに加え、「人間中心のAI」という視座を取り入れた、より包括的な枠組みづくりが求められている。
HCAIが中心に据える「人間中心のAI」の考え方は、テクノロジーの進化とい人間らしさの共存を通じて、互いの特性を活かし合いながら新しい価値を生み出していくための考え方である。
それは、AIの時代における人間のあり方と創造性の本質を問い直す実践的な取り組みであり、技術開発の枠を超えた人間とAIの共生のビジョンを示すものだといえるだろう。

