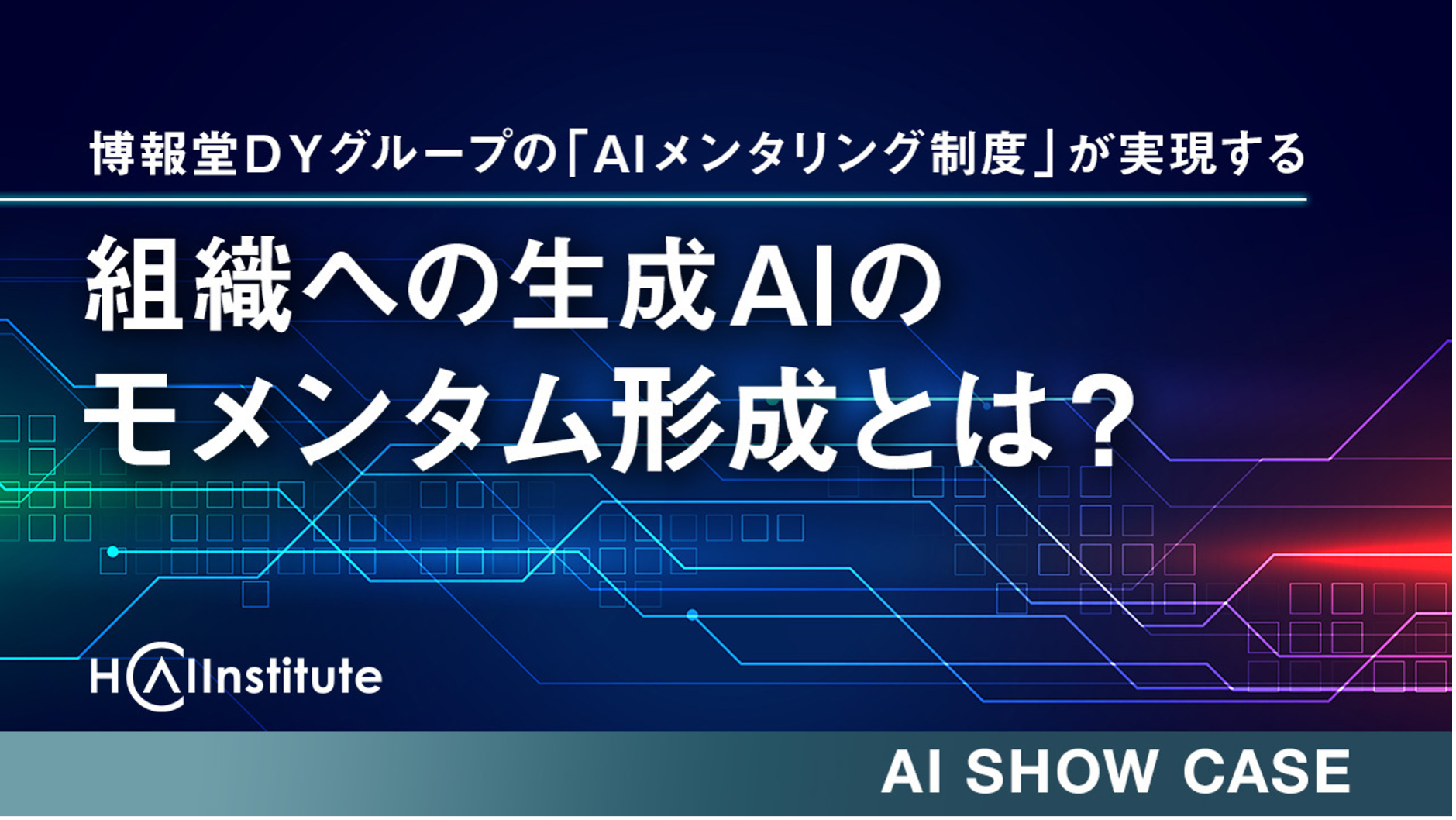
博報堂DYグループの「AI
「生成AIの社内普及を進めたいが、経営層の関与が小さい」「旗振り役となるべき経営層が生成AIを十分に使いこなせていない」
生成AIを使いこなせるかどうかが企業の競争力に直結する時代において、生成AI活用のムーブメントを全社的に起こすためには、経営層の先導が重要だ。一方で、多くの企業において経営層が十分に生成AIを理解していない・使いこなせていないという現実がある。
そうした中、株式会社Hakuhodo DY ONEでは、ある企業にて経営層向け「マンツーマンAIメンタリング」による生成AI活用支援を行っている。今回は、この取り組みについて同社の中原に聞いた。
<著者プロフィール>
株式会社Hakuhodo DY ONE
チーフAIストラテジスト
中原 柊

大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系SaaSスタートアップを経て、現職。テクノロジーの進化と、生活者や市場の変化を見据えた課題解決を得意とする。メディア/Webサービス/通信/エネルギー業界を中心に、事業創造、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。現在は、コンサルティング事業の立上げをミッションに、AI活用や新規事業を支援するコンサルティング事業を中心として、外部講演への登壇や記事執筆などを通じた情報発信活動にも注力。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)がある。
生成AI活用推進のポイントとなる「経営層へのアプローチ」
従業員全体に生成AI活用のモメンタムを作り上げていくうえで、キーとなるのが「経営層へのアプローチ」だ。各従業員に対して生成AI活用のためのサポートを展開していくことはもちろん重要だが、それではどうしても個々人の取り組みにとどまってしまう。組織的な生成AI活用を進める上では、各部門の管掌役員が自らAIを触り、AI推進の意義を認識し、自部門へ生成AI活用の重要性を発信していく必要がある。
このような認識のもと、博報堂DYグループでは「AIメンタリング」制度を導入した。この制度は、積極的にAIを活用している若手社員の中からAIメンターを選出し、ペアとなる博報堂DYグループの経営層に対し定期的に生成AIツールのトレーニングやサポートを行うものだ。若手のAIメンターが経営層に生成AIに関するサポートを行う一方で、経営層は自身の経験知や知見を若手社員に提供する、相互補完的なプログラムとなっている。
AIメンターは経営層の関心に応じた最新のAIに関するトレンドを共有するだけでなく、経営層の業務と親和性の高い生成AIツールを経営層自ら操作してもらい、効果的な使い方やプロンプトの工夫をサポートする。これにより、経営層からの生成AI推進の意識づけ、活用促進を狙っている。
AIメンタリング制度を導入した結果、参加した経営層の月間AI利用回数は約3倍になった。加えて、若手社員がAIを活用して得意先マーケティング支援の最前線で活躍することへの経営層への期待も高まった。
博報堂DYグループ「AIメンタリング」制度を導入
経営層と若手社員によるペアワークでAI活用を加速化
https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2025/08/5771.html
Hakuhodo DY ONEによる「経営層へのアプローチ」の支援事例
博報堂DYグループでは、この取り組みを社外にも広げている。Hakuhodo DY ONEでは、ある大手企業に向けて生成AIの活用推進を支援しているが、そこでもやはり「経営層へのアプローチ」を重要視している。
今回支援を行った大手企業は従業員数も多く、全員に対して生成AI活用のためのアプローチを行っていくのは現実的ではない。そこで、優先的なターゲットの一つとして、経営層を選択した。経営層は日常的に細かな業務を行う立場ではないため、直接的に生成AIを使う機会は限られる。しかし、経営層がその可能性を理解し、戦略立案や取引先とのコミュニケーションといった場面に応用することで、組織全体に与えるインパクトは大きい。さらに、経営層が生成AI活用の重要性を認識し、管掌する組織に波及させていくことによる効果も極めて高い。組織内に向けて発信を行ってもらうためにも、まずは経営層生成AIを理解してもらい、実際に触れてもらうことが重要だ。
本支援のポイントは「1 to 1」だ。経営層に向けたアプローチ方法として集合型研修も支援内容に含まれているものの、主となる施策は「AIメンターによる1 to 1での経営層向けのメンタリング」としている。各役員の中でもAIに関する知識にはバラつきもあり、関心のある領域も様々だ。また、集合型研修を行うために全役員を一堂に集められるのはせいぜい2時間が限度といえる。そこで、集合型研修はあくまで生成AIの基本情報をインプットすることに注力し、「AI・生成AIで何ができるのか」「AIの今後と求められる企業変革」「他社や世間の動向」「自社の現在地」といった、誰もが知っておくべき事項を中心に解説を行った。その後は博報堂DYグループでの事例と同様にAIに精通した若手社員をAIメンターとして任命し、1 to 1によるメンタリングを中心とした取り組みとした。
経営層が生成AIを理解し、発信することの効果
生成AI活用のモメンタムを作り上げ、生成AIを組織に定着化させていくために重要なのは「経営層からの発信」だといえるだろう。実際にHakuhodo DY ONEでも、各部門の管掌役員が生成AIに関する発言や発信を行うことで、社員も生成AI活用の必要性を認識するという流れが生まれている。
今回、支援内容に集合型研修と1 to 1でのAIメンターによるメンタリングを含めたのも、役員による発信のインプットとしてほしいという想いからだ。役員が自身の言葉で生成AIの必要性について発信してもらうことを目標とし、そこから逆算して今回の支援内容を検討した。本支援では、最終的に施策の様子や成果、経営層のビジョンを社内ポータル・Teamsなどで定期発信することにより、取組みや想いを通じた全社モーメントを醸成することを目指している。
費用対効果の観点からも、経営層をターゲットとした取り組みの重要度は高い。企業において生成AIの活用推進を行う際には、投資対効果を問われることとなる。本事例でも同様に費用対効果の算出を行ったが、その算出において経営層向けアプローチによる全社への波及効果は非常に高く見積もられている。従業員のAI活用を底上げできるという観点で、特に従業員数が多い企業においては経営層向けにアプローチすることは費用対効果の高い施策となるだろう。
共通の課題感を持つ企業は多い
今回は「AIメンターによる1 to 1での経営層向けのメンタリング」を導入いただいた、ある大手企業の事例 を紹介したが、生成AIの活用推進に課題感を持たれている企業は非常に多いという印象だ。特に、各企業のDX部門においては、生成AIの活用がミッションとなっているケースが多く、どのように自社に生成AI活用のモメンタムを生み出していくか悩まれている方も多いだろう。そのような企業において、経営層向けのアプローチは費用対効果の観点も含め有効な選択肢となる。特に博報堂DYグループや今回紹介した事例のように、AIメンターが1 to 1で役員にサポートを行う取り組みは、座学では得られない実践的な経験を役員にインプットできるという点に優れる。
人口減少時代において、生成AI活用は限られた労働力で最大のパフォーマンスを出すために必須といえる。企業においては、生成AIをいかに組織に定着化させていくか、そのための取り組みが求められている。

